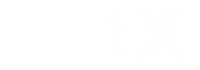映画とDXの関係性
現在、映画とデジタルは切っても切れない関係となっております。
変貌を重ねるCGやデジタル技術によって映像の世界は様々な世界を演出することがより可能になりました。
特にハリウッドなどのSF、ファンタジーの世界を描く上で、デジタル技術は欠かせません。
今回はそういった、最新のデジタル技術によって映像作品がどのような変化を遂げているか、また、昨今の映像業界の変化が私たちの生活にどの様な影響を及ぼしているかを示していきたいと思います。
映画の歴史
そもそも映像作品はどのようにして変化してきたのでしょうか?
今では実写の鮮明さだけでなく、今やアニメーション作品も現実の世界にあるかのような繊細さや立体感を持ち、3D技術も合わされば、目の前に飛び出し、手を伸ばせば届くような錯覚さえ抱くことができます。
そこに辿り着くまでの変貌とはどのようなものだったのか、映画の歴史を振り返ってみましょう。
映画初期時代

映画の始まりは1895年、フランスにてリュミエール兄弟が公開した作品「ラ・シオタ駅への列車の到着」が起源とされています。
映写機は発明家として有名なエジソン、また、フランスの発明家ルイ・ル・プランスなどが開発をしておりましたが、現在の映画館に通づる「スクリーンに映像を映し、多くの人が同時に鑑賞できる」というスタイルを築いたのはリュミエール兄弟です。
それまで、情景映像ばかりでストーリー・役者などの概念がなかった映画に「娯楽」としての要素を取り入れたのはフランスの奇術師、ジョルジュ・メリエスでした。メリエスも最初は自身のマジックを映像で収めるだけのものでしたが、1902年にはストーリーの要素も含んだ「月世界旅行」を制作しました。
しかしまだこの頃は、もちろん世界中どこも無声の映像ばかりです。
トーキー・カラーの登場

その後、世界では1927年に世界初のトーキー(有声)映画として「ジャズ・シンガー」が公開され、大きな変革をもたらしました。
ちなみに、日本ではトーキー映画が成功をしたのは1931年「マダムと女房」。
当時、日本で映画は「活動写真」と呼ばれており、世界でも稀な「活動弁士」という無声映画に情景や台詞を実況する「説明」を担う職業が活躍していました。
一つの文化を支える職業の必要性がなくなるということで、日本でのトーキー映画の出現は大変大きな出来事となったのです。
さらなる変革をもたらしたのは1932年、カラー映画の登場です。
それまでにもカラーフィルムの開発は行われてきましたが、青や黄色が表現できないなど、色彩再現力が不完全なものでした。
しかし、それらの欠点を克服した三原色式の改良版テクニカラーが開発され、そのシステムがディズニー・シンフォニーシリーズの短編映画「花と木」で初めて採用されました。
さらに、ディズニー社は5年後に世界初のカラー長編映画「白雪姫」も完成させたのです。
映像に臨場感や説得力を与えさせるカラー映像に加え、当時としては珍しいマルチプレーンカメラの使用をするなどして世界中から注目を集め、現在でもアニメ史に残る傑作となっています。
音が鳴り、色がつき、より「目で見た世界」に近づいた映像の衝撃は強く、画面内の汽車が近づく臨場感に驚き、思わず劇場を飛び出した人もいたそうです。
映画界において特に1930〜1940年台はハリウッド黄金期と呼ばれ、年間400本もの映画が制作されましたが、デジタルの技術は登場しておらず、SFX(いわゆる特殊撮影)を用いての映画制作が行われていました。
多数の模型やミニチュアの火薬、フィルムの重ね撮りなど様々な技術が駆使され、現実ではありえない世界や、現象を作り出していたのです。
デジタル技術の登場

映画などの映像作品にデジタル技術(CG)が利用されるようになったのは1982年に制作された「トロン」が最初の作品です。
この頃はまだ全編がコンピュータで制作されてはおらず、96分中の15分程度がCGとなっています。この頃はまだコンピューターグラフィックスの費用が高く、多くはCGに見せかけた手書きのアニメーションが使用されていました。
世界初のフルCGアニメーション映画は1995年、ピクサー・アニメーション・スタジオによって制作された「トイ・ストーリー」です。
ディズニーとピクサーが共同でCG制作システムを作り、この作品では81分の全編が3DCGを用いて制作されています。
昨今では、CG技術を駆使した作品が日々増え続けていますが、CGの作品の歴史は意外とまだまだ浅いものなのです。
近年の撮影によるデジタルコンテンツの変化

ではDX化の急速に進む撮影業界では、近年どのような変化が起きているのでしょうかご紹介しましょう。
皆さんは「CG合成」や「CG背景」と聞いて何を思い浮かべるでしょうか?
多くの方が想像するのはクロマキー合成、いわゆる、グリーンバックやブルーバックで撮影されたものにコンピュータグラフィックを合成する、というものではないでしょうか。
もちろん今でもそういった撮影方法で撮られている作品はいくつもあります。しかし、グリーンバックやブルーバックなどの撮影にも問題点がいくつかあります。
例えば、背景と交わる境界部分や毛先などがうまく合成されず、背景色が残ってしまったり、フルCGの作品などではセットはおろか、登場人物までもがモーションキャプチャーのためグリーンスーツに身を包んでいたりと、全世界がのっぺりとした単色の空間になるため、俳優の想像力や演技力が非常に試されます。
その後の合成においても用意した背景画像に俳優の視線が合致しているのか、瞳に背景の色移りがしていないかなど細かな部分の調整が必要になります。
そこで登場したのがバーチャルプロダクションやステージクラフトと呼ばれる、LEDスクリーンによるバーチャルセットです。
270度囲まれた巨大なLEDスクリーンに、本来なら撮影後に合成されていた背景画像を映し出すことで、より臨場感のある撮影をすることができるようになりました。
俳優、監督、スタッフ陣は、ともに世界感をリアルタイムで共有することができるため、アングルや演技プランの修正・決定が即座に行えるようになります。
また、実在の場所があるとしても、実際にロケ地に行く必要もなくなるため、天候を気にしなくても良いほか、コロナ禍において人の流れが非常に抑えられます。
使用にかかる費用は大きいですが、その他の作業工程の大幅な削減や作業時間が短縮されるようになるため、今後、こうしたバーチャル撮影を使用した作品はますます増えていくことでしょう。
俳優に関わるDX

次に、CGではない実際の人物・俳優にとっては、DX化によりどのような変化がもたらされているのかご紹介します。
先ほど紹介したバーチャルセットはもちろん、役者にとって大きな変化となりました。
もちろん役者にとって想像力も不可欠なものですが、実際に目に入った景色があるに越したことはありません。
そしてもう一つ、近年のDX化により、より作品にリアリティの出るようになったものがあります。それは「AI技術による若年化や老年化」です。
ハリウッド映画でも大変な人気を誇っているアベンジャーズシリーズを例にご紹介しましょう。
特に2019年に公開され、大きな話題を呼んだ「アベンジャーズ・エンドゲーム」は近年のデジタルコンテンツが様々な場面で活用されています。
マーベル作品において時間軸の交差はよくあるのですが、この作品では特に多く、約200ショットでディエイジング・及びエイジングのエフェクトが施されました。
特殊メイクで極端に老けさせる、などではなく、AI技術によるエフェクトで、時間軸に合わせて5歳分など非常に細かな調整を加えて撮影されているのです。
若い時の同じ役を、年齢に合わせた別の役者を使用する必要がなくなるため、観客はこれまでよりさらに作品に集中し、キャラクターやストーリーに感情移入がしやすくなりました。
また、この作品において重要な役所のサノスや、初期の作品から登場し、活躍をしているハルクなどはフェイシャル・キャプチャを使用し、より実際の俳優の表情や動きに近いものが繊細に緻密に表現されています。
近年の技術革新により、さらに細かな毛や皺の表現が可能になり、よりリアルさが増した存在感となっています。
映画配給のDX化

そして、変革しているのは制作の現場だけではありません。
それら最新技術を駆使して作られた作品を、観客の元へとお届けする配給側でもDX化は進んでいます。
例えば、今や当たり前のように浸透している、ネットフリックスやHULUなどのサブスクリプション動画配信媒体「VOD(ビデオオンデマンド)」の登場は映像業界における大きな変革となりました。
レンタルショップに行かなくても、自宅にいながら過去の映画やテレビ番組が見られることは、より動画を身近なものにしました。
「いつでもどこでも」が叶う動画配信サービスは、出張などの自宅以外への移動が多い人や、学生の休憩時間、お子様連れの方が家事に集中したい時など、多くの場面で様々な世代の方が利用することができ、大きな支持を得ています。
また、ネット限定の番組が増えたり、コロナ禍により自宅で過ごす時間が増えたことで、サブスクリプションの動画配信サービスは年々利用者数を増やし続けています。
映画館ではネットでチケットが購入できるデジタルチケットが導入され、コロナ禍でも接触を最小限に抑えることができています。
そして、3Dメガネを使用することにより映画の世界観が目の前に飛び出してくるような感覚を味わえる、3D映画に加え、最近では「体感型」と呼ばれる4DXの登場も注目されています。
映画の映像に合わせて座席の上下左右の可動や、背面への衝撃、地響き、耳や首へのエアー、その他「水」「風」「香り」「煙」「バブル」「熱風」など、様々な環境効果が体感できるプログラムが開発され、組み込まれ、映画の世界のそのまま入り込んだような時間を楽しむことができるようになりました。
まとめ〜今後の映画業界の未来と期待〜

最後に今後の映画業界で想定されるものや問題についてお話をしましょう。
デジタル技術の進む映画業態でよく言われるのが、「俳優の喪失」です。今後CGが進歩していけば、思いのままの動きをする、思いのままの外見をしたCGの俳優を作るなどわけないことになっていくかもしれません。
今でもほぼCGで創造されたキャラクター(先述したサノスやハルクなど)も多くおり、「俳優の必要性とは?」ということが問われています。
しかしながら、スタッフ陣は今、細かな表現が可能になったからこそ、役を担っている俳優の繊細な目の動きや毛の流れ、微妙な筋肉の動きなど、「その人自身にしか出せない表情」を表現することに尽力しています。
生身の人間が演じるからこそのものとCG技術の発達が、この後どのような関わり方や変化をしていくのか、期待が高まります。
また、映画・動画を見る媒体が増える可能性もあります。
それは「VR空間」への可能性です。
2018年より、バーチャルマーケットと呼ばれる、「仮想空間上での3Dアバターや3Dモデルの展示会」が開催され始めました。そこで注目したいのが、2020年にVR空間内で再現された映画館です。
この年に開催されたバーチャルマーケットでは六本木のTOHOシネマズが再現され、マーベルシリーズ最新作の「ブラックウィドウ」の最新予告動画が観られたり、ブラックウィドウ一色に装飾された映画館で、写真撮影ができたりしました。
世界がまさにコロナに脅かされ、日本でも大規模な自粛が余儀なくされていた時期に、VRの空間では、「仲間と一緒にお出かけ」が叶っていたのです。
映画館、動画配信サービスでの視聴に加え、VR映画館で、家にいながら最新の映画と友人と観られる。
もしかしたら、そんな未来もそう遠くないのかもしれません。今後の映像業界のDX化もますます目が離せません。