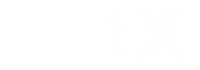「IT企業が取り組むことのできるSDGs活動とDX推進」は、IT企業がデジタル技術を活用して、どのように社会課題の解決に貢献できるのか?をSDGsと紐付けながら考えるシリーズです。
シリーズ第2弾となる本記事のテーマは”教育”。教育に関してどのような課題があるのか?IT企業はデジタル技術を活用してどのように解決に貢献できるか?考えを深めていきたいと思います。
SDGs 目標4「質の高い教育をみんなに」とはどんな目標?

SDGsの目標4は、「すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する」というテーマに基づいて、10個のターゲットで構成されています。
目標4のターゲット概要は以下の通りです。
- 全ての子どもが、無償かつ質の高い、就学前教育/ケア・初等教育・中等教育を受けられる
- 全ての若者が、高い技術教育・職業教育・高等教育を受けられる
- 全ての人が、持続可能な社会のため、生涯を通して知識や技術を習得できる
すべての人々が質の高い教育を受けられることで、以下のような社会の実現につながると言われています。
- 子どもの健康管理や出産を安全に行うことができる
- 就業できる仕事の幅が広がることで収入向上、貧困から抜け出すことができる
- 児童婚や早すぎる妊娠を減らすことができる
- 高次産業の担い手が増えることで1次産業以外の産業が発達、経済成長につながる
質の高い教育は、人々の生活の質を改善し、社会が持続的に発展していくための基盤となります。貧富の差や環境、性別に関係なく教育を受けられる環境を整えることが今求められているのです。
教育に関する国内外の課題
教育に関して国内外にどのような課題があるのか改めて確認しておきましょう。
世界的な課題
もともと、2030年までに目標4を達成することは難しいと推定されていました。そしてCOVID-19による学習機会の損失によってその状況は一層困難を極めている状況です。
- 2億人以上の子どもたちが学校に通えていない(COVID-19以前の推計)
- 15歳以上で字の読み書きができない人は7億5000万人、その3分の2は女性
- 少なくとも5億人はオンライン学習環境がない
- 50%以上の学校はインターネットやコンピューターの設備が整っていない
日本の課題
一方、日本では義務教育によって教育水準は世界的にも高いものの、以下のような問題があることも事実です。中でも深刻な問題が”子どもの貧困”。”子どもの貧困”は親が非正規雇用などで給料が少ないことが原因となっているケースが多く、学歴や教育との関連性は否定できません。
- 小・中・高合わせて少なくとも23万人の生徒が不登校
- 7人に1人の子どもが相対的貧困状態にあり、教育格差につながっている
- 学習障がいの生徒へのケアが十分にできていない
- 研究者に占める女性の割合は12%と低い
- 54%の社会人が「時間的」「金銭的」制約によって学ぶ意欲はあるものの学べていない
「質の高い教育をみんなに」にIT企業はどのように貢献できるのか?
では、IT企業はICTを活用して、どのように”教育”の課題に貢献できるのでしょうか?身近に取り組むことのできる日本の課題を解決する一例を見てみましょう。
オンライン授業環境
まずは、オンライン授業の環境整備をサポートすることがあげられます。コロナ禍による休校が相次ぐ中で、環境整備は進んでいるものの、特に地方においてはまだ遅れている状況があります。
オンライン授業の環境を整えることで、災害時にも教育を継続できる、不登校や病気などの理由で学校に通えない生徒にも教育の機会を与えることができる、都心と地方の教育格差をなくすことができる、などまさにSDGsへの貢献と教育現場のDXを実現します。
また、民間の学習塾や生涯学習スクールにおいては、オンラインに切り替えることで、利用者の時間的・場所的制約を排除して利便性を高め、売上向上の機会にすることもできるでしょう。
アダプティブラーニング
IT企業は、アダプティブラーニングの仕組み構築にも貢献することができます。
アダプティブラーニングとは、学習者の理解度に合わせて、一人一人に合わせた学習内容、学習方法を提供していく教育方法です。蓄積された学習ログを解析し、事前に設定したアルゴリズムやルールに沿って、次の設問の選定や学習カリキュラムの作成を自動で行うものです。これまでの教育は、大勢に対して、同じ教育を施すことが大半でしたが、アダプティブラーニングによって、学習障がい*がある子供も、苦手な学習を諦めることなく自分のペースで進められるようになり、より質の高い学習を実現します。
また、アダプティブラーニングは、一方的で画一的な授業がつまらないと感じている生徒や、周りと比べられることで必要以上に苦手意識を持ってしまっている生徒にとっては魅力的な点であり、高校・大学・専門学校などで利用すれば、少子化の状況でも生徒を集めるためのアピールポイントとなり得るでしょう。
学習障がい:基本的に全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する、推論する、推論する能力のうち特定のものの習得・使用が困難であること。学習面で困難を示す児童生徒は4.5%存在する。
VRによる実習・実験
VRを用いた実験や実習のサポートをすることも可能です。現在コロナ禍における3密回避策によって、医療系や理工系などの実習に遅れが出ている状況があります。例えば医学部における解剖実習については、義務であるにも関わらず実習時間の短縮や、看護学生の見学不可といった問題も起こっています。しかし、ここでVRを利用することができれば、遠隔で実習や実験に参加することができるだけでなく、全方位映像で確認したり、その場で分からないことを調べたり、チャットで質問するといったことができるようになり、効率的な学びを推進することができます。
校務効率化
日本の教員の労働環境は決して楽とは言えず、残業は当たり前の状況です。校務を効率化するさまざまなシステムやツールを利用することで、教員の負荷を低減し、より良い学習環境の整備や、生徒のメンタルサポートなどにリソースを割くことができるようになります。そしてこれは学習の質の向上につながります。校務効率化システムとしては、生徒情報管理システムの導入、採点や評価業務の自動化、出欠表や出張届けなどの紙媒体で作成・提出している事務作業の電子化などが考えられます。
教員から雑務を手放し、本質的な課題に集中できる環境を整えることで、学習の質を向上させられるだけでなく、教員のモチベーション維持や働き方の改善にも寄与します。また、私立学校や民間の学習機関としては、優秀な教員を集めるポイントにもなり得るでしょう。
まとめ
この記事では、SDGs目標4の「質の高い教育をみんなに」について、IT企業が貢献する方法について検討してきました。文部科学省も「GIGAスクール構想」を打ち出し、日本の教育環境のデジタル化は一層進むことが予想されます。ICTを活用することによって、今後更に、すべて人への質の高い教育の提供、教育現場の変革が進んでいくでしょう。IT企業はこれまで培ったノウハウを活用してそのパートナーとして並走していくことが期待されます。
(参考資料)
UN:SDGs Report 2021
UN:About the Sustainable Development Goals
公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン:子どもの貧困と教育格差
文部科学省:令和元年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について
内閣府:経済諮問会議資料
文部科学省教育のデジタル化に関する主な取組について
経済産業省:EdTechを活用した学校現場の業務改善等検討事業
(SDGs活動とDX推進シリーズ 記事一覧)